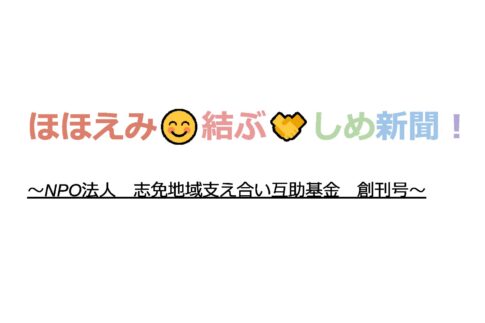- 申請書のどこに何を書けばよいのか分からない
- 活動の目的や内容をどう表現すれば伝わるのか不安
- 審査で「通る」申請書に共通する書き方を知りたい
助成金申請は、団体の活動を広げる大きなチャンスです。
しかし、実際に書類を前にすると「どう書けば伝わるのか」「この表現で十分なのか」と不安になる方は少なくありません。
そこで、初めての方でも安心して取り組めるように、通りやすい申請書の書き方を3つのポイントで解説します。
ポイント1:活動の目的を一文で明確にする

冒頭に目的をシンプルに書く
申請書の最初の段階で「この活動は何のために行うのか」を一文で表現しましょう。
長く書く必要はなく、短くわかりやすくまとめることが重要です。
審査員に一目で伝わる
審査員は短時間で多くの申請書を読みます。最初に目的がぼんやりしていると、後に続く活動計画や予算書の理解も難しくなります。
逆に冒頭で明確に目的を示すことで、その後の文章も「なるほど、この目的のためにこの活動をするのだな」と一貫性を持って読んでもらえます。
誰に・どんな効果をもたらすかを書く
- 「地域の高齢者が孤立せず、安心して暮らせる居場所をつくる」
- 「子育て中の親が悩みを共有できる交流の場を提供する」
- 「障がいのある子どもたちが安心して学べる環境を整える」
このように 「対象(誰に)」+「効果(どうなる)」 を短い文章で示すと、目的が具体的に伝わります。
書き方のポイント:主語と動詞をはっきりさせる
「~のために」「~を目指して」といった表現を使うと、活動の方向性が伝わりやすくなります。
- 「地域住民が安心して暮らせる環境を整えるために交流活動を実施する」
- 「子どもの健やかな成長を支えるために学習支援を行う」
短く書くことが信頼につながる
目的を簡潔に一文で伝えることは、審査員に「この活動は必要だ」と思ってもらうための第一歩です。
読み手が迷わず理解できる目的の提示こそ、通る申請書づくりの土台になります。
ポイント2:活動内容を数字と具体例で示す

活動の実現性を数字で裏付ける
活動内容は「何を、どれくらいの規模で、どのくらいの頻度で行うか」を数字で表現しましょう。
数字を入れることで計画の説得力が増します。
あいまいな表現では伝わらない
「交流会を開きます」「子育て支援を行います」だけでは、活動の規模や実現性が伝わりません。
審査員は「その団体が本当に計画通りに活動できるのか」を確認します。
参加人数や開催回数、期間などを数字で明記することで、実行力がある計画だと判断されやすくなります。
数字で表すとこう変わる
- 曖昧な書き方:「地域の人が集まる交流会を開催します」
- 具体的な書き方:「月1回30名規模の交流会を町民センターで開催し、年間12回実施します」
また、応募要項でも「実現可能性」「継続性」が選考基準とされています。
したがって、数字を盛り込むことは審査基準にも直結します。
書き方のポイント:数字+場所+期間をセットで書く
活動内容を書くときは、次の3点を意識すると効果的です。
- 数字:人数・回数・割合(例:参加者30名、年6回、アンケート回答率8割)
- 場所:具体的な会場や地域(例:志免町公民館、町内の小学校体育館)
- 期間:実施する期間や頻度(例:2025年6月~翌年3月、月1回)
この3つを組み合わせることで、活動内容がイメージしやすくなります。
数字は信頼性の証明になる
具体的な数字を盛り込むことで、活動計画が現実的であることを審査員に伝えられます。
数字は「信頼できる団体である」という証明にもつながるのです。
ポイント3:期待される効果をわかりやすく書く

成果を具体的に描く
活動の結果として、地域や参加者にどのような変化や効果が期待できるのかを、具体的にわかりやすく書きましょう。
助成金の趣旨は「地域への貢献」
助成金は「地域社会のニーズに応え、支え合いや互助に貢献する事業かどうか」が重要な基準です。そのため、成果を明確に示せば、「この事業は地域の役に立つ」と判断してもらいやすくなります。
効果の書き方
- 「交流会を通じて高齢者の孤立感を減らし、アンケートで参加者の8割が『元気が出た』と回答」
- 「子ども食堂を実施することで、月30名の子どもに栄養ある食事を提供し、地域ボランティア20名の関わりが生まれた」
- 「学習支援教室を行い、参加した児童の7割が『勉強が楽しい』と答えた」
このように 定性的な効果(孤立感が減った、元気が出た)+定量的な効果(8割が回答、30名に提供) を組み合わせると説得力が高まります。
書き方のポイント:効果は「見える化」する
- アンケートの結果を数値化する(例:満足度○%)
- 参加者数や活動回数を成果として書く
- 地域への広がり(例:町内新聞に掲載、次年度は2地区に拡大予定)
審査員に「活動の波及効果がある」と感じてもらえるよう、数値や具体的な変化を書き添えると効果的です。
効果を書くことは社会的価値のアピールになる
期待される効果を具体的に描くことで、助成金を出す意義が明確になります。活動が地域にどんな未来をつくるのかを伝えることが、採択への大きな後押しとなります。
まとめ:通る申請書に近づく3つの秘訣!

助成金申請書を書くときは、次の3点を意識してください。
- 活動の目的を一文で明確にする
- 活動内容を数字と具体例で示す
- 期待される効果をわかりやすく書く
この3つを押さえることで、初めての申請でも自信を持って提出できる申請書に仕上がります。
審査員に「この活動は地域にとって必要だ」と感じてもらえるよう、シンプルかつ具体的に書くことが大切です。
👉 詳しい申請手順や提出書類については、志免地域支え合い互助基金の助成金ページをご確認ください。