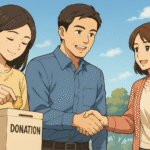2025年10月4日(土)13:30より、2025年度活動報告会が開催されました。
外が真っ白になるくらいの大雨のなかではありましたが、40数人の皆さまが会場にお見えになって下さいました。
皆さま、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
90分と短い時間ではありましたが、活動報告・志免清龍隊さんの演舞・シンポジウムを行わせて頂きました。活動のほんの1部ではありますが、皆さまにご報告ができたと思います。
また、志免清龍隊さんに於かれましては、1曲の演舞時間しか取れませんでしたが、幼児から60代までが一緒にヨサコイ演舞を行う素晴らしさを魅せて頂きました。ありがとうございます。
そして最後のシンポジウムでは、立場や年齢の違う方々に、
①志免町で生活している時に、暮らしやすいと感じる時・暮らしにくいと感じる時
②10年後の2035年。あなたは志免町で暮らしていると思いますか?
③10年後の2035年、どんな志免町であって欲しいですか?
④その為に、自分にできる事。貢献出来ることは何ですか?
について質問をさせて頂き、ご意見を述べて頂きました。
このシンポジウムでは、志免中学校3年の岡出葵さんが参加をして下さいました。
支え合い新聞社の社長をされています。
町を歩いて投稿する中学生。車の運転をしないので、どこにいくにも歩きが基本です。従って、いろんな場を観たり、いろんな人と出会ったり、すれ違ったり、朝・昼・夜の町の顔を知っています。これは、運転免許を返納したり、車に乗らない高齢者の皆さんと同じです。
中学生には、その目があるのです。その目が。
大人だけで行う対話や話し合いの場では、偏った意見しかでないことが多い。しかし、中学生の皆がその話し合いに入ると、歩く方の意見が入ってきます。それは幼児や小学生、高齢者等の方々の意見も入ってくるという事に繋がります。
今回のシンポジウムを通じ、町づくりの話し合い・対話をする際に、やはり多世代が参加した場である事。そして、その場をコーディネートする人がいること。そして、そこで出る意見をまとめ、次なる企画に結びつける人がいること。それが大事になります。
段々と行うべき事が絞れてきたと共に、核心に迫っているように感じます。
これも偏に、NPO法人志免地域支え合い互助基金を信じ、ご支援を頂く皆さまのお陰です。
NPO法人志免地域支え合い互助基金は、今後も志免社会のお役に立てれるよう、仕えて参ります。どうぞ、よろしくお願い致します。